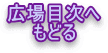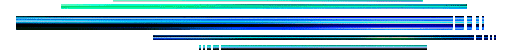
6年「鳴り砂研究発表」
| 室蘭には、全国でも珍しい「鳴り砂」のある「イタンキ浜」があります。 私たちは、その鳴り砂について調べてみました。 |
| 鳴り砂とは |
|
| 鳴り砂とは、砂浜海岸をつくる砂がよく乾燥したとき、棒の先などで、押したり踏みつけたりして、摩擦を与えると「キュッキュッ」という美しい音を発する砂のことをいっています。 鳴り砂の美しい音色は、晩秋から初春のよく晴れた日にきかれます。 また、砂がよく鳴るためには、粘土やシルトを含まずに、砂の表面がきれいであることが必要であります。 鳴り砂海岸は日本中に数ヶ所あるといわれていますが現在全域にわたってよく鳴る砂浜はわずかほどになってきています。 鳴り砂にもいろんな音があり、鳴りのよい時から鳴りの悪い時の音まで全ぜん音がちがいます。 1. ゲロゲロ 2. グヮングヮン 3. ケロケロ 4. ンギュンギュ など、色々あります。 |
| どうして音がなるの | |
| 【どうして?なんで?砂が音を?】 きれいな表面を有した砂が、擦れあう場合に摩擦音として発生しています。現象としてはガラスコップをきれいに洗って、指で擦ったときに音が出るのと考えてもらえれば良いかと思います。工学的には静的な摩擦と、動的な摩擦が繰り返されて、あのような音がでています。 【鳴り砂と普通の砂とはどうちがうのですか】 グランドの砂や砂場の砂は、砂の表面に粘土のような小さな粉がくっついています。それは鳴り砂にはなりません。また海岸の砂のように絶えまなく洗われていませんので、表面は汚れて傷がついています。全く表面の光沢がありません。それでは、鳴りません。砂で山を作ると、鳴り砂の砂は高い山となり普通の砂は低い山になります。 |
| 鳴り砂になる条件 | |
| (1) 砂粒の大きさ・・・0.2から0.6mm程度の砂浜 (2) 石英砂に富んでいること (3) 砂粒の形が丸みを帯びている。 ※ これは、結果的に自然の砂は長年の月日 でそうなっています。鳴り砂を人工的に作って 光顕微鏡的に観ると、自然の鳴り砂のように 必ずしも丸くなっている必要はないことがわ かってきました。 (4) きれいな海であること (5) 海が安定している。土砂などがいつも流れ込んできて いない。 (6) いつもきれいな水で洗われていること。 ※ 実は、水で洗われている必要はありません。 砂漠にも鳴り砂はあるんですから。でも日本 のような海岸の鳴り砂は、きれいな水でなけ ればなりません。 |
| 室蘭の鳴り砂 | |
| アイヌの人たちがつけた地名ハワノタ(声ある砂浜)に基づき、イタンキ浜一帯の砂浜を昭和61年に調査したところ、日本でも有数の“鳴り砂”であることが実証されました。“鳴り砂”とは、砂同士の摩擦でキュッキュッと澄んだ音がするものです。 その条件は、 1. 砂に長石やガラスの材料となる石英粒が多いこと 2. 砂に丸みと艶があること 3. 砂の粒が適度の大きさでそろっていること そして最も大事なことは 4. 油やゴミなどで汚染されてないことです イタンキ浜は、浜全体が、“鳴り砂”海岸ですが汚れなどで自然の状態で音が出る場所はかなり限定されています。なかでもトッカリショ側の白っぽく乾いた砂の条件が良いようです。 【音の出し方】 足で強く擦るように歩くか、手で強く擦ると良いでしょう。また、ワイングラスなど、底の丸いグラスに砂を入れ、棒などで突くと可愛い音を出します。平成9年3月に市民団体による「イタンキ浜鳴り砂を守る会」が発足し、砂浜の清掃などの保護活動を行っています。 |
| 久末進一さんのお話 | |
| 【室蘭市民俗博物館の久末進一学芸員さんの話】 昭和60年ごろにイタンキ浜に「はわのた」という場所があるという伝説があった。そこでどこにそういう場所があるか調べた。はわのたはそういう言葉になるまえは「はわんおた」という。「はうわんおた」の意味は声がする砂という意味だった。みんなでさがしてその場所に目印の旗をたてた。ところが1週間ごその砂浜はただの砂浜になっていた。つまり鳴り砂の浜は波によって動いていた。だから長い間「はわのた」の場所がわからなかった。そして鳴り砂の場所もわからなかった。それからすぐ見つかった。鳴り砂は最初は白老川の川上から運ばれて海の底にたまって波で運ばれてイタンキの浜にうちあげられてたまった。それから海がよごれてきて鳴らなくなってきた。その理由は砂にあぶらがついてよごれてしたったからだ。まだ今は鳴くけどこれから鳴らなくなってしまうなと心配しています。室蘭だけじゃなくて鳴り砂は日本中にキレイな海に鳴り砂はある。 【世界の鳴り砂】 世界の鳴り砂では、まずはアメリカのシカゴのそばにそういう鳴り砂の場所がある。世界の人々の一人一人のよびかた。ミュージカルサントに音楽砂スインギングサンドに歌う砂こう呼ばれてます。日本ではなり砂のことを泣き砂と呼ぶ人もいる。中国では鳴砂という人もいす。鳴砂山もある。鳴砂山はかいぶつの山と呼ばれていた。アフリカにもあるコンゴ川という所にも鳴り砂があります。イギリスにはうエッグ島(たまご)にみつかった。室蘭にも鳴り砂の歌はいっぱいあるらしい。鳴り砂には石英分がたくさんふくまれている。約70%以上あると鳴り砂ができる。石英はふつうの砂よりかたい。 |